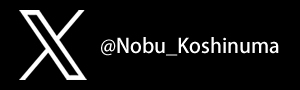室生寺には法隆寺についで古い五重塔があります。
桧皮葺の屋根やたん塗りの組み物が奥深い樹林にか囲まれて格別の風情があります。
そして山奥の神秘的なシャクナゲの寺でもあります。

仁王門。近代に再建されています。

太鼓橋

五重塔
五重塔は800年ごろ(平安時代)のものです。
高さは16mで興福寺の五重塔の1/3ほどです。
初重と五重目の屋根の大きさがあまり変わらず、屋根に厚みがあって深いのが特徴です。

この日は晴れていましたが、雨上がりのような湿気というか潤いがありました。

階段の上にあるため、見上げる姿が美しいです。

この角度からみる五重塔も絶景です。周りの木がとても大きいです。

木々が生い茂っています。この潤いが植物を育てるのですね。

金堂。緑が深くてとても美しいです。

金堂。江戸時代のものです。

この階段で奥ノ院に登ります。
1998年の台風でそばの50mの杉が倒れた際に屋根が壊れる被害を受けました。
心柱を含め被害が少なかったので損傷せずに修復することができました。
その際に当初の木材の年輪から794年に伐採されたものだと判明したそうです。
年輪からそこまで詳しくわかるなんて本当にすごいですね。

雨をもたらす龍神が棲むとされる室生山。
五重塔から奥ノ院に向かう途中の山肌にはイヨクジャク、イワヤシダなど天然記念物に指定された暖地性のシダ群生が見られます。
これは主に四国、九州以南に生息する種で近畿圏で目にすることは大変珍しいものです。
山頂に清水寺のような足組の建物があります。

山奥にこんな大きな建物を作るなんてすごいですね。

女性に人気のお寺だけあってハート形に集められていました。

金堂の前に大きな木があります。
室生山の山麓から中腹に塔などが広がっています。
770年(奈良時代)の山部親王の病気平癒のために興福寺の僧が朝廷の命でここに寺院を作ることになりました。
その後、代が変わり現在の伽藍が整うまでには相当の年月を要したと考えられています。
創建に係わったのが興福寺の僧だったため室生寺は長らく興福寺との関係が深かったそうです。
奈良時代にたくさんのお寺が建てられていますが、その時代の天皇陛下、皇后さま、僧侶などいろんな繋がりがあったのですね。

鎧坂。とても美しい石段です。

仁王門。緑に朱色が映えます。
室生寺は女人高野と言われ、江戸時代から女性にも参拝が許されていました。
境内にはシャクナゲ、紅葉などたくさんのお花が迎えてくれます。

仁王門。
近鉄大阪線室生口大野駅から室生寺まで6キロほどのハイキングコースを歩くのもいいですね。

室生寺
【住所】〒633-0421奈良県宇陀市室生78
【TEL】0745-93-2003
【FAX】0745-93-2057
【アクセス】バス
近鉄室生口大野駅から室生寺前行バス終点下車徒歩5分
【駐車場】
普通車100台(有料)
【拝観料】
大人:600円
子供:400円