奈良市登大路町にある南都七大寺のひとつ興福寺。現在、興福寺は「古都奈良の文化財」の一部として世界遺産に登録されています。
興福寺は、古代から中世にかけて巨大な勢力を誇った藤原氏の氏寺。前身は藤原鎌足の病気平癒のために夫人の鏡女王が京都山科に建立した山階寺(やましなでら)となります。
その後、山階寺(やましなでら)が藤原京に移ってからは、厩坂寺(うまやさかでら)と名称が変わり、現在の地に移転し「興福寺」と名付けられました。
もくじ
世界遺産 興福寺の住所、拝観時間、拝観料、駐車場、アクセスなど
| 【訪問地】興福寺 【所在地】奈良市登大路町48番地 【電話】0742-22-7755 【公式URL】 https://www.kohfukuji.com/ 【拝観時間】9:00~17:00(国宝館、東金堂、中金堂) 【拝観料】境内無料 【駐車場】周辺に民間駐車場あり 【アクセス】車ナビに「興福寺」または「0742-22-7755」とご入力ください。 近鉄奈良駅から徒歩5分 JR奈良駅からバスで5分 |
世界遺産 興福寺 アクセスマップ
興福寺 五重塔(国宝)

猿沢池より。
興福寺・五重塔(国宝)は、光明皇后の発願により、天平2年(730年)に創建されました。現在の塔は、応永33年(1426年)頃に再建されたものとなります。
高さは50.1mあり、現存する国内の木造塔としては、東寺の五重塔に次ぐ高さとなります。


上の写真は奈良県庁の屋上から興福寺五重塔を撮影したものですが、近鉄奈良駅から徒歩3分とは思えない素晴らしい景色です。
東大寺の大仏殿や若草山、生駒山、葛城山、金剛山など、奈良を代表する山々も望むことができます。
あまり知られていないこともあり、屋上ベンチでのんびり過ごすこともできますよ~。夏は日差しが強いのでおすすめできませんが、春先、秋は、ランチ持参がオススメ。
興福寺 五十二段 修行の石段

猿沢池の目の前にある興福寺に続く石段。石段が52段あることから「五十二段」と呼ばれています。
「52」という数字は、仏道で悟りを開くためにの菩薩の修行の段階をあらわした「菩薩五十二位」の「52」に由来しています。
興福寺 五重塔と東金堂(国宝)

国宝の五重塔と東金堂。
写真中央の東金堂には、銅造薬師三尊像(重要文化財)、国宝の木造維摩居士(もくぞうゆいまこじ)が安置されています。
慶応4年(1868年)の「神仏分離令」で、全国に仏教を排する動き(廃仏毀釈)が活発となりました。ここ興福寺も一時は廃寺同然となっていて、五重塔も三重塔も売りに出されていたそうです。
興福寺南大門跡 トイレ

2018年に完成した中金堂(ちゅうこんどう)の目の前に位置する「興福寺南大門跡」。ここは元々お寺の正面玄関だったところです。
江戸時代中頃(1717年)に焼失してからは再建されることなく現在に至っていますが、奈良文化財研究所が発掘調査を行い、南大門の規模が明らかになりました。
現在は東西30mにもなる巨大な基壇が復元され、礎石も再現されています。基壇のスケールからすると平城宮跡にある朱雀門と同じくらいの大きさがあったのでは・・・と言われています。

上の写真は五重塔前にある塀ですが、奥にトイレが設置されていますので、覚えておくと良いかもしれません。
興福寺 南円堂

重要文化財に指定されている南円堂。
南円堂は弘仁4年(813年)に藤原冬嗣が父の藤原内麻呂(うちまろ)の冥福のために建立した建物です。
「西国三十三所」の第九番札所として多くの人が参拝している御堂です。
南円堂内には、
国宝の「木造不空羂索観音菩薩坐像(ふくうけんさくかんのんぼさつざぞう)」「木造四天王立像(してんのうりゅうぞう)」「木造法相六祖坐像(ほっそうろくそざぞう)」が安置されており、毎年10月17日のみ公開されています。
南円堂の御朱印は、上写真の右側にある納経所にて授与していただけます。


南円堂の八角形の屋根中央にある美しい「宝珠飾り」。
興福寺 百度石

興福寺南円堂前にある「百度石」。
「百度石」というのは、神仏に祈願するために百度参拝することを言います。元々は、毎日、百日続けて参拝することを指していたのですが、なかなか時間も取れないことや距離的な問題もあるため、一日に百日参るという形になったそうです。「百度石」は、この他に「百度参り」または「お百度を踏む」とも言われています。
興福寺 中金堂

2018年10月に落慶した「中金堂(ちゅうこんどう)」。 ※写真中央が中金堂
中金堂は興福寺伽藍の中心になる最も重要な建物ですが、創建以来なんども焼失と再建を繰り返してきました。享保2年(1717年)の火災以後は100年以上も再建されず、文政2年(1819年)に篤志家の寄付によって再建(仮の堂)されました。
1819年時に再建したときの建物は、当時のものよりも一回り以上も小さかったそうです。安価な建築資材が使われたこともあり、瓦や経年による雨漏りもひどくなり、301年ぶりに新たに再建されました。
再建にあたっては、受け継がれてきた伝統的な木工技法を踏襲し、できる限り古式の工法が採用されています。
興福寺 北円堂(国宝)

日本にある八角円堂のなかで、最も美しいとされる興福寺の北円堂(国宝)。この建物は藤原不比等の一周忌にあたる養老5年(721年)に元明・元正天皇が、長屋王に命じて建てさせたものです。
興福寺北円堂内には、本尊である弥勒如来坐像 (みろくにょらいざぞう) 、無著(むじゃく)・世親菩薩立像(せしんぼさつりつぞう)をはじめとして、木心乾漆四天王立像などが安置されています。
興福寺 三重塔(国宝)

興福寺で最古の建物となる三重塔。
高さ19m、本瓦葺きの三重塔は、1952年に文化財保護法に基づく国宝に指定されています。

三重塔と南円堂。
三重塔(国宝)は、少し奥まったところにあり、目立たないことから観ることなく帰られてしまう方も多いと聞きます。興福寺北円堂前の参道を南に行くと見えてきますので、ぜひ忘れずにお立ち寄りくださいね。
御朱印をいただける場所
興福寺で御朱印をいただける場所は、下記の通りです。
| 【場所】 中金堂前授与所・・・「中金堂」「令興福力」「東金堂」「千手観音」「興福寺 御詠歌」「稚児観音」「菩提院大御堂 御詠歌」 南円堂前授与所・・・「南円堂」「南円堂 御詠歌」「令興福力」「一言観音」「大職冠持佛」「神仏霊場巡拝の道 第16番」「西国観音曼荼羅」 ※「北円堂」の御朱印は期間限定 【時間】9:00~17:00 【初穂料】200~500円 【御朱印帳】1,300円 |
| ■興福寺周辺の観光地 「東大寺」「興福寺」「春日山原始林」「元興寺」「奈良公園」「若草山」「ならまち糞虫館」 など |
| ■奈良の世界遺産 「東大寺」「興福寺」「春日大社」「春日山原始林」「元興寺」「平城宮跡」「薬師寺」「唐招提寺」「法隆寺」「法起寺」「吉野・大峰」 ※順不同 |
| ■京都の世界遺産 「上賀茂神社」「下鴨神社」「金閣寺」「龍安寺」「仁和寺」「銀閣寺」「延暦寺」「高山寺」「東寺」「西本願寺」「二条城」「清水寺」「西芳寺」「天龍寺」「醍醐寺」「平等院鳳凰堂」「宇治上神社」 ※順不同 |
【訪問地】興福寺
【所在地】奈良市登大路町48番地
【電話】0742-22-7755
【公式URL】 https://www.kohfukuji.com/
【拝観時間】9:00~17:00(国宝館、東金堂、中金堂)
【拝観料】境内無料
【駐車場】周辺に民間駐車場あり
【アクセス】車ナビに「興福寺」または「0742-22-7755」とご入力ください。
近鉄奈良駅から徒歩5分
JR奈良駅からバスで5分





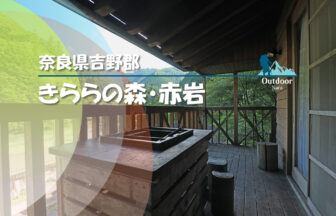



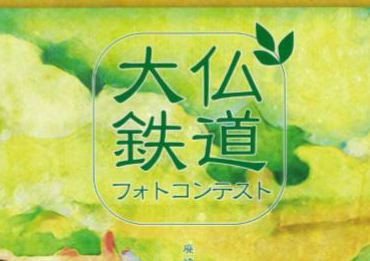













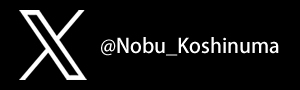



この記事へのコメントはありません。